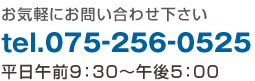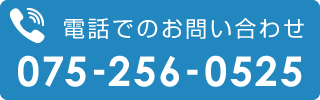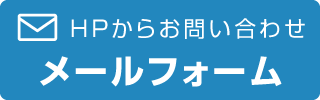Author Archive
保証契約の際の説明義務に注意しましょう(債権法改正関連NO1)
平成29年5月、民法(債権法)が120年ぶりに改正され、3年程度の周知期間を経て施行される見通しです。改正項目は多岐にわたるですが、企業経営者の方に影響が多くありそうなところから機会をみてご紹介していきたいと思っております。
今回はその第1回目として個人保証についてその個人保証人の保護方策の拡充、ひっくり返すと個人保証を取得するときの留意点になるともいえます。その一部について触れたいと思います。そのなかで私が特にきになっているところは、保証契約締結の際の情報提供義務です。
条文を下記に掲載してありますのでご参照ください。
とても簡単に言いますと、保証契約をするときに、主たる債務者から、その主債務者の財産及び収支、主たる債務以外の債務の有無、額、返済状況、担保についての状況を保証しようとするものに説明しなければならないという情報提供義務が定められたということと、その情報提供がなされていないときには、他の条件もあるのですが、保証契約を取り消しできるということです。
保証契約をする人、保証契約を取得する債権者、保証をお願いする債務者などはこの点をしっかりと注意しましょう。十分な説明を受けていなければ保証契約を取り消しできる場合があること、債権者、主債務者からすれば、保証契約が取り消されててしまう場合があることを十分注意しましょう。
「(契約締結時の情報の提供義務)
第465条の10 第1項 主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、次に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
一 財産及び収支の状況
二 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
三 主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
第2項 主たる債務者が前項各号に掲げる事項に関して情報を提供せず、又は事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者がその事項について誤認をし、それによって保証契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合において、主たる債務者がその事項に関して情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り又は知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができる。
第3項 前2項の規定は、保証をする者が法人である場合には、適用しない。」。

京都市や大阪市、神戸・西宮・芦屋など京阪神エリアを中心に、身近な法律問題に丁寧に向き合っています。
24年間の金融機関勤務経験を活かし、法人・個人を問わず、ご相談いただいた方の立場に寄り添った対応を心がけています。
相続や離婚、交通事故、債務整理など、日常に関わる法律問題もお気軽にご相談ください。
不安、悩みは必ずしも法律問題だけではないと思います。心の不安、悩みを軽減、解消するためにカウンセリング業務にも取り組んでおります。
債務整理、破産など借入の整理についての初回の法律相談は無料。ご予約を頂ければ夜10時までご相談できます。お気軽にお問い合わせください。
外国の方が関係する相続について(渉外相続)
【被相続人が日本以外の国籍を持つ方、相続財産が外国にある方などの相続など】
被相続人が日本以外の国籍を持つ方、相続財産が外国にある方などの相続をまとめて渉外相続と言われます。
日本の民法だけでは対応することができず、どうしたらよいのか迷う方もおられると思います。
日本で多いのは例えば、在日韓国人のケースではないでしょうか。国籍は韓国ですが、居住は日本にあり、財産も日本にある。
このような場合はどのようになるのでしょうか。
外国が絡む場合は、準拠法といって、どこの国の法律が適用されるのかをまず決める必要があります。
相続における準拠法は、原則として被相続人の本国法(法の適用に関する通則法36条)によります。
(少しむつかしいのですが、反致によって、常居所地法や不動産所在地法としての日本法が適用される場合があります。
反致とは、法廷地である日本の法律(国際私法)によれば外国法が準拠法になりますが、その指定された外国法(国際私法)によりますと日本法が殉教法になり場合に外国法の国際私法を考慮して、法廷地である、日本法を準拠法とする場合をいいます)
国によって被相続人が準拠法を選択できる旨、立法しているものがあります。
韓国もその一つです。原則は本国法ですが、常居所地法や不動産所在地法を遺言で選択することができます。
従いまして、在日韓国人の方も、遺言で、日本法を準拠法として選択ができることになり、日本法を準拠法として遺言で選択した場合は、慣れしたんでいる民法で相続手続きをすることができるといえます。
遺言で指定がなされていなければ、本国法である韓国法が適用されることになり、例えば、日本の民法の、相続人の範囲や相続割合の規定とは異なることになります。
日本法とはかなり異なる場合がありますので十分注意する必要があります。
被相続人が日本以外の国籍を持つ方、相続財産が外国にある方などの相続などの場合は、専門家にすることをお勧めします。
test1234

京都市や大阪市、神戸・西宮・芦屋など京阪神エリアを中心に、身近な法律問題に丁寧に向き合っています。
24年間の金融機関勤務経験を活かし、法人・個人を問わず、ご相談いただいた方の立場に寄り添った対応を心がけています。
相続や離婚、交通事故、債務整理など、日常に関わる法律問題もお気軽にご相談ください。
不安、悩みは必ずしも法律問題だけではないと思います。心の不安、悩みを軽減、解消するためにカウンセリング業務にも取り組んでおります。
債務整理、破産など借入の整理についての初回の法律相談は無料。ご予約を頂ければ夜10時までご相談できます。お気軽にお問い合わせください。
変形労働時間制とフレックスタイム制をご紹介
労働時間制度シリーズ第4弾
労働時間制度に関する記事もこれで4回目となりました。
第1回からお伝えさせて頂いておりますが、会社の実態に即した労働時間制を採用することが、生産性の向上やコンプライアンスに結実していきます。
第2回と第3回を通して、変形労働時間制とフレックスタイム制をご紹介させて頂きました。
この2つは、企業の労働時間の設計についての制度です。
労働時間の設計を変えることで、原則的な労働時間(1日8時間、週40時間)を変更し、労働実態に即した労働時間制度を採用できるというものです。
また、労働法では、労働時間の設計の変更のほかにも、労働時間の算定の方法によって法定労働時間の制限を解除する特例も設けられています。
労働時間の算定についての特例にもいくつかの制度がありますが、今回はその中でもみなし労働時間制についてご紹介いたします。
みなし労働時間制とは、簡単に言うと実際に何時間労働したかにかかわらず、一定時間労働時間働いたものとみなすという制度です。
この制度には、「事業場外労働のみなし制」や「専門業務型裁量労働制」、「企画業務型裁量労働制」という細かい区分けがあります。
この3つの区分けは、それぞれ特徴が違っており、業務形態によりどれを採用するのが良いかが変わってきます。
「事業場外労働のみなし制」(労働基準法38条の2)は、事業場(オフィス)外の業務で、業務時間の算定が困難な外回り営業や報道記者等の場合に適しています。また、出張の場合にもこの制度が用いられることがあります。
「専門業務型裁量労働制」(労働基準法38条の3)は、研究開発、情報処理システムの分析、デザイナー等の労働者の裁量が大きいとされる業務が対象とされます。もっとも、この制度は、厚生労働省令で定められた業務しか対象とできません。
「企画業務型裁量労働制」(労働基準法38条の4)は、経営や社内組織、財務等企業の運営に関する企画立案を業務とする場合に適した制度です。
このように、労働時間のみなし制はそれぞれ適した業務がありますが、導入手続きが複雑なうえ、制度が複雑なこともあってか厚生労働省の調査によると全体の8.4%程度しか利用されていないようです。
ただ、それぞれ特徴のある制度ですので、業務の実態に即していれば、導入することで生産性の向上やコンプライアンスが図られると思います。

京都市や大阪市、神戸・西宮・芦屋など京阪神エリアを中心に、身近な法律問題に丁寧に向き合っています。
24年間の金融機関勤務経験を活かし、法人・個人を問わず、ご相談いただいた方の立場に寄り添った対応を心がけています。
相続や離婚、交通事故、債務整理など、日常に関わる法律問題もお気軽にご相談ください。
不安、悩みは必ずしも法律問題だけではないと思います。心の不安、悩みを軽減、解消するためにカウンセリング業務にも取り組んでおります。
債務整理、破産など借入の整理についての初回の法律相談は無料。ご予約を頂ければ夜10時までご相談できます。お気軽にお問い合わせください。
労働時間制度について
労働時間制度シリーズ第3弾
労働時間制度に関する記事もこれで3回目となりました。
第1回から労働時間制度についてお伝えさせて頂いておりますが、労働基準法32条で定められている労働時間制度は、社会の多様化に即して柔軟な制度が設けられています。
厚生労働省の調査によると、前回ご紹介した変形労働時間制の内1年単位のものを採用している企業は30.6%、1か月単位のものを採用している企業は20.3%に上るそうです。
このように、変形労働時間制を採用している企業は、50%を超えています。
今回は、労働時間制度のうちのフレックスタイムについてご紹介させていただきたいと思います。
フレックスタイム制(労基法32条の3)とは、それぞれの日に何時から何時まで業務をするかを従業員の自由に任せる代わりに、1週40時間・1日8時間の法定労働時間を超えても、清算期間における法定労働時間の総枠を超えない限り時間外労働とならないとする制度です。通常は、出退勤できる時間(フレキシブルタイム)が定められ、全員が必ず出席すべき時間(コアタイム)が定められる場合もあります。
この制度を採用することで、従業員は出退勤時間を自由に決められることで従業員のワークライブバランスに貢献でき、ひいては企業の生産性向上につながると言われています。
もっとも、出退勤時間が自由になるため、従業員間のコミュニケーションに時間が減ったり、チームメンバーがいないために作業効率が落ちたりするという弊害も考えられます。
実際、伊藤忠では、一時期フレックスタイム制を採用していましたが、2012年には廃止しています。また、厚生労働省の調査でも、全体の導入率は4.3%に留まるそうです。
フレックスタイム制では、どのように内容を策定するかも重要ですが、どのように運用していくのかがとても大切です。運用の方法によって、会社の創造性・生産性を向上させる労働時間制にもなりますし、逆も状況になってしまうこともあり得ます。
このようにフレックスタイム制は、導入に際しては自社の実態に即しているかを運用面まで含めてよく検討する必要があります。
また、導入に際しては、就業規則の変更(策定)、労使協定の締結等などの手続きも必要となってきます。
もし、このようなフレックスタイム制にご興味のある方は、弁護士にご相談ください。フレックスタイム制を導入すべきかどうかも含めて、会社の実体に即した労働時間制のご提案をさせて頂きます。また、フレックスタイム制の運用についても、ご対応させて頂きます。
担当 坂口俊幸法律事務所 弁護士 山口晃平

京都市や大阪市、神戸・西宮・芦屋など京阪神エリアを中心に、身近な法律問題に丁寧に向き合っています。
24年間の金融機関勤務経験を活かし、法人・個人を問わず、ご相談いただいた方の立場に寄り添った対応を心がけています。
相続や離婚、交通事故、債務整理など、日常に関わる法律問題もお気軽にご相談ください。
不安、悩みは必ずしも法律問題だけではないと思います。心の不安、悩みを軽減、解消するためにカウンセリング業務にも取り組んでおります。
債務整理、破産など借入の整理についての初回の法律相談は無料。ご予約を頂ければ夜10時までご相談できます。お気軽にお問い合わせください。
交通事故に遭ってしまったときまず、どうすればよいのか
交通事故の被害者になったら
~初期行動~
交通事故の被害にあったら、どのように行動すれば良いのでしょうか。
意識を失うことが伴うような大けがを負ったのなら、病院で治療を受けるしかないのですが、今回は、体の一部を痛めたといった軽い怪我を前提とします。
行動すべき簡単な流れを示すと①警察を呼ぶ②事故の相手方の連絡先を確認する③病院に行って治療してもらう④病院から診断書をもらう⑤診断書を警察に提出する(⑥完治するまで治療を続ける)ということになります。
この流れのなかで、よく相談を受けるのが⑤診断書を警察に提出するという点です。事故直後に受診した病院で発行された診断書を警察に提出すると、当該事故は人身事故として扱われ、診断書を提出しないと物損事故として扱われることになります。
この違いは何かというと、人身事故となれば、運転手(加害者)は自動車運転過失致傷という刑事責任を負うことになり、それに加え、行政処分としての免許の点数も引かれ、免許停止等になる可能性が生じます。他方、物損事故扱いであれば、そのようなことは生じません。
そのため、加害者側から人身事故扱いにしないで欲しいと持ち掛けられるのはこれが理由となります。
また、物損事故だと誰もケガをしていないことになりますので、加害者側が加入している保険会社より治療費等は原則として支払われることはありません(手続き次第では保険会社に治療費を支払ってもらえる方法はあります)。
ですので、ケガをされた場合には、特別な事情が無ければ診断書を警察に提出して人身事故扱いにされるのが良いでしょう。
次によくある相談が、交通事故後数日して、治療中にも関わらず、加害者側から示談を持ちかけられた場合に示談してもよいかどうかという相談です。
加害者に求めに応じて示談された場合、その後、示談した金額より治療費等がかかったとしても、示談後に加害者から追加で支払いの請求することは困難です。
したがって、示談は治療を終了してからにしましょう。
交通事故の被害に遭われるといろいろと手続きをとらなければなりません。
治療を受けながら、よくわからない手続きをしないといけないというのは、精神的にかなりの負担になります。
交通事故の手続きに不安を感じたら、すぐに相談されるのが良いでしょう。
弁護士に相談するタイミングは、早いにこしたことはありません。
相談するだけでも気持ちが楽になるはずですよ。

京都市や大阪市、神戸・西宮・芦屋など京阪神エリアを中心に、身近な法律問題に丁寧に向き合っています。
24年間の金融機関勤務経験を活かし、法人・個人を問わず、ご相談いただいた方の立場に寄り添った対応を心がけています。
相続や離婚、交通事故、債務整理など、日常に関わる法律問題もお気軽にご相談ください。
不安、悩みは必ずしも法律問題だけではないと思います。心の不安、悩みを軽減、解消するためにカウンセリング業務にも取り組んでおります。
債務整理、破産など借入の整理についての初回の法律相談は無料。ご予約を頂ければ夜10時までご相談できます。お気軽にお問い合わせください。
交通事故における後遺症の判断
交通事故の被害者になったら
~後遺症について~
交通事故でケガをされたとき、まずは病院で治療されることと思います。
そのあと、気になることは、自分のケガが後遺症になるのではないかという点です。
ところで、この後遺症というのはどういうことでしょうか。また、だれがどのように判断するのでしょうか。
後遺症について、医師が判断すると思っている人もおられるかもしれませんが医師の役割は、後遺症かどうかを判断するにあたって、患者さんのケガの状況を診断書に記載することであって、医師が後遺症を判断するのではないのです。
すなわち、医師が書いた診断書をもとに、後遺症に該当するかどうかを判断する別の機関があるということです。実際には、自賠責調査事務所の調査結果をもとに自賠責保険会社が判断します。
次に、どういった場合に後遺症と判断されるのでしょうか。
そもそも、後遺症というのは、簡単に言えば、ケガが完治せず、このまま治療を継続しても回復する見込みがない状態のことをいいます。たとえば、関節の一部が動かなくなったりとか、失明したりというようなものです。
この後遺症の判断は、医師が書いた診断書とともに、MRI画像等、客観的な資料を参考にしつつ判断されます。
そして、交通事故のケガでの後遺症で、最も皆さんが直面する可能性が高いのが、首や腰が継続して痛むいわゆるムチウチというものがあります。
このムチウチも、痛みが継続的に残るわけですから後遺症に該当し得ます。具体的な後遺症でいうと「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)というものになります。
ところが、このムチウチ症状が、後遺症の判断にあたって、最も厄介なものだったりします。
先ほども述べたように、後遺症に該当するかどうかは、診断書とともにMRI画像といった客観的な資料を基に判断します。
しかし、ムチウチの場合、首や腰に痛みはあるのに、MRI画像等には、その原因となるものが映らないというのが多々あり、診断書以外の客観的資料がない場合があるのです。
そのため、首や腰の痛みが残っているのに、後遺症と判断してもらえないという人が多数おられます。そして、その結果として、交通事故にともなう損害賠償も、けがに対する十分な補償を受けることができないということがあります(後遺症に該当するかどうかで、損害賠償の金額は大きく変わります)。
交通事故でケガをされた場合、後遺症が残らないことが最も良いことです。
しかし、中には治療を継続しても、痛みがなくならないこともあるでしょう。その場合、後遺症ということになりますが、後遺症の判断には医学的な面と法律的な面と双方に問題となります。後遺症についての適切な補償を受けるためにもお近くの専門家に相談されるのがよいでしょう。
坂口俊幸法律事務所 弁護士 奥田尚彦

京都市や大阪市、神戸・西宮・芦屋など京阪神エリアを中心に、身近な法律問題に丁寧に向き合っています。
24年間の金融機関勤務経験を活かし、法人・個人を問わず、ご相談いただいた方の立場に寄り添った対応を心がけています。
相続や離婚、交通事故、債務整理など、日常に関わる法律問題もお気軽にご相談ください。
不安、悩みは必ずしも法律問題だけではないと思います。心の不安、悩みを軽減、解消するためにカウンセリング業務にも取り組んでおります。
債務整理、破産など借入の整理についての初回の法律相談は無料。ご予約を頂ければ夜10時までご相談できます。お気軽にお問い合わせください。
労働時間制度シリーズ第2弾
労働時間制度シリーズ第2弾
前回は、会社の労働時間制度について、様々な制度があり、会社に適した労働時間制度を採用することが大切です、とお伝えしました。
今回は、そのうちの変形労働時間制についてご紹介致します。
変形労働時間制とは、単位となる期間内において所定労働時間を平均して週法定労働時間(1週間40時間)を超えてなければ、期間内の一部の日や週で法定労働時間を超えても、時間外労働との扱いにしないという制度です。
少しわかりにくいですが、このような変形労働時間制には、1か月単位のもの(労働基準法32条の2)、1年単位のもの(労働基準法32条の4)、1週間単位のもの(労働基準法32条の5)があります。
1か月単位の変形労働時間制は、1か月以内の一定期間を平均して1週間40時間を超えていなければ、予め定めた特定の週や日が40時間や8時間を超えても良いというものです。この制度は、1か月の中で繁閑の激しい企業や深夜交代制の業務(タクシー等)、一昼夜交代制の業務に適しています。
1年単位の変形労働時間制は、1年以内の一定期間を平均して1週間40時間をこえない定めをすれば、予め定めた特定の週・日において1週40時間・1日8時間を超えることができるというものです。この制度は、デパートのように1年の中で特に繁忙時期(お中元・お歳暮等)を持つ企業や結婚式場等に適しています。1年単位の変形労働時間制では、日給月給制を用いている会社であれば、所定労働時間に応じて月々の賃金が変動しますが、月給制として定額に定めることも可能です。なお、当然ですが、変形労働時間制で定めた労働時間を超えた分には割増の賃金が必要です。
1週間単位の変形労働時間制は、1週間40時間の枠内であれば1日10時間まで労働させることができるというものです。ただ、この1週間単位の変形労働時間制は、厚生労働省令で定められた特定の事業(常時30人未満の小売業・旅館・料理店等)についてのみしか認められていません。
変形労働時間制の概要はこのようになっていますが、その内容はわかりやすいとは言えません。また、導入手続きも労使協定を策定したりと煩雑なことが多いです。
そのため、多くの方は変形労働時間制を導入すれば良いのかどうかもわからないのではないでしょうか。
しかし、多くの労働時間制の中から、会社に適した制度を選択することが会社の発展につながることは間違いありません。
変形労働時間が適しているか、その他の制度も含めてご興味のある方は、弁護士にご相談ください。企業の実体に即した労働時間制のご提案をさせて頂きます。
担当 坂口俊幸法律事務所 弁護士 山口晃平

京都市や大阪市、神戸・西宮・芦屋など京阪神エリアを中心に、身近な法律問題に丁寧に向き合っています。
24年間の金融機関勤務経験を活かし、法人・個人を問わず、ご相談いただいた方の立場に寄り添った対応を心がけています。
相続や離婚、交通事故、債務整理など、日常に関わる法律問題もお気軽にご相談ください。
不安、悩みは必ずしも法律問題だけではないと思います。心の不安、悩みを軽減、解消するためにカウンセリング業務にも取り組んでおります。
債務整理、破産など借入の整理についての初回の法律相談は無料。ご予約を頂ければ夜10時までご相談できます。お気軽にお問い合わせください。
労働時間制度シリーズ第一弾 電通の新入社員の過労自殺と労働時間法制
最近、電通の新入社員の方が、過労を苦にして自殺してしまったという痛ましい事件がありました。
この事件では、月100時間を超える過度の残業時間が問題となりましたが、そもそも、法律上の労働時間はどのように定められているのでしょうか。
労働基準法32条では、労働時間は、原則として1日8時間、1週間で40時間以内と定められています。そのため、多くの会社は、5日間8時間+週休2日という労働時間を採用していると思われます。
もっとも、最近では、ユニ・チャームが製造現場を除く全社員を在宅勤務制度としたように、多様な働き方に合わせて労働時間の配分も多様になってきています。
法律では、このような社会のニーズに応えるために、変形労働時間制(週の法定労働時間の枠内に、一定の単位期間の週当たりの労働時間数の平均が収まっていれば良いという時間制度)やフレックスタイム制(1か月等の単位で一定時間数労働すれば、1日の始業と終業を自由に定められる時間制度)などを認めています。
このように労働時間を柔軟化する制度のほかに、三六協定(サブロクキョウテイ)というものもあります。
本来、会社が時間外労働をさせることは許されず、従業員にどうしても時間外労働をしてもらいたい場合には、三六協定という労使協定を締結することで、上限はありますが時間外労働をしてもらうことができます。余談ですが、三六協定は、労働基準法36条に定められているので、「三六(サブロク)」と名づけられました。
冒頭で取り上げた電通でも、労使間で三六協定を締結していました。
会社の業務形態や経営方針に合わせて、最適な労働時間制度を選ぶことが何よりも大切です。最適な労働時間制を採用することで、従業員にとって働きやすい環境を提供でき、ES(従業員満足)の向上、ひいてはCS(顧客満足)の向上を図ることができます。また、無駄な残業時間もなくなります。
逆に、その会社に適さない労働時間制度を採用してしまうと、長時間の残業が増えるにもかかわらず、生産性は低いままという状態を招いてしまうことになりかねません。
もし、自分の会社が適した労働時間制を採用しているか気になった方は、我々弁護士にも相談してみてください。各種の労働時間制を踏まえてサポートをさせて頂きます。
担当:坂口俊幸法律事務所 山口晃平

京都市や大阪市、神戸・西宮・芦屋など京阪神エリアを中心に、身近な法律問題に丁寧に向き合っています。
24年間の金融機関勤務経験を活かし、法人・個人を問わず、ご相談いただいた方の立場に寄り添った対応を心がけています。
相続や離婚、交通事故、債務整理など、日常に関わる法律問題もお気軽にご相談ください。
不安、悩みは必ずしも法律問題だけではないと思います。心の不安、悩みを軽減、解消するためにカウンセリング業務にも取り組んでおります。
債務整理、破産など借入の整理についての初回の法律相談は無料。ご予約を頂ければ夜10時までご相談できます。お気軽にお問い合わせください。
交通事故の被害者になったら~弁護士に相談するメリット
交通事故の被害者になったら~弁護士に相談するメリット~
交通事故の被害に遭ったら、まず皆さんはどのように行動されるでしょうか。
たとえば、①警察に連絡する②病院に行く③家族に連絡するというのが思いつきます。
今回知っておいていただきたいことは、④「弁護士に相談してみる」ということです。
なぜ、④「弁護士に相談してみる」ことを勧めるかと言いますと、
皆さん、交通事故に遭った後、どのように手続きが進むかご存知でしょうか?、また保険会社との交渉をご自身で全てやっていくことに不安があるのではないでしょうか?
弁護士や保険会社で働いたことのある方を除いて、自信をもって大丈夫といえる人はほとんどいないと思います。
交通事故の処理は、警察での刑事手続はもちろんのこと、自賠責保険に対する請求、後遺症の認定請求等極めて複雑なうえ、関係機関も沢山あることから、一般の方がご自身だけで対応するのはとても難しいです。
しかも、交通事故の被害に遭った方は、このような手続の不安もさることながら、怪我が治るか、後遺症が残らないかを不安に思いながら日々治療に行かれているはずです。
そのため、そういった手続きの不安を解消し、治療に専念するためにも、弁護士に相談されることをお勧めします。
また、弁護士に交通事故の処理を依頼すると、保険会社との最終的な合意金額が増額する場合があります。
私が扱った事件で、後遺症もなく通院のみで治療が終了した方の事件があります。この事件では、当初、保険会社からの最終的な解決金としての保険金は約80万円でした。
しかし、その後、依頼者の掛かっていた病院のカルテを十分に精査して、保険会社と再交渉したところ、最終的に約160万円で解決することができました。当初金額から2倍も増額したということになります。
もっとも、弁護士に相談すれば、どの事件もこのように大きく増額するというわけではありません。
しかし、保険会社が提示する金額は総じて低い場合が多く、適切な示談金額になっていない場合があります。
そこで、私たち弁護士は、適切な金額を目指して保険会社と交渉します。
このように、弁護士に相談することで、事故後の手続きや保険会社との交渉の不安を取り除き、最終的な示談金額も適切な金額になるというメリットがあります。
他方で、弁護士費用が高くつくのではないかとの不安もあるかと思います。
この弁護士費用についても、色々とお話しすることはありますが、それは次の機会で。
担当:坂口俊幸法律事務所 弁護士奥田尚彦

京都市や大阪市、神戸・西宮・芦屋など京阪神エリアを中心に、身近な法律問題に丁寧に向き合っています。
24年間の金融機関勤務経験を活かし、法人・個人を問わず、ご相談いただいた方の立場に寄り添った対応を心がけています。
相続や離婚、交通事故、債務整理など、日常に関わる法律問題もお気軽にご相談ください。
不安、悩みは必ずしも法律問題だけではないと思います。心の不安、悩みを軽減、解消するためにカウンセリング業務にも取り組んでおります。
債務整理、破産など借入の整理についての初回の法律相談は無料。ご予約を頂ければ夜10時までご相談できます。お気軽にお問い合わせください。
遠隔地の方、スカイプでの相談(有料)も承ります。事前にご予約お願いします。
遠隔地の方でもスカイプでのご相談もできます。
是非、事前にご相談ください(有料となります)

京都市や大阪市、神戸・西宮・芦屋など京阪神エリアを中心に、身近な法律問題に丁寧に向き合っています。
24年間の金融機関勤務経験を活かし、法人・個人を問わず、ご相談いただいた方の立場に寄り添った対応を心がけています。
相続や離婚、交通事故、債務整理など、日常に関わる法律問題もお気軽にご相談ください。
不安、悩みは必ずしも法律問題だけではないと思います。心の不安、悩みを軽減、解消するためにカウンセリング業務にも取り組んでおります。
債務整理、破産など借入の整理についての初回の法律相談は無料。ご予約を頂ければ夜10時までご相談できます。お気軽にお問い合わせください。